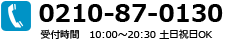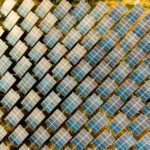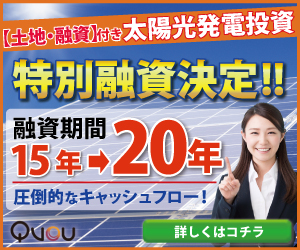国内で、電力自由化がはじまったのは2016年4月です。
施行から2年が経ち、電力自由化によって生まれた問題点や課題が浮き彫りになってきました。
一方、アメリカでは日本より20年も早く電力自由化が実施されています。
我が国で電力自由化によって起こっている問題点を、アメリカの事例から考え、その課題やデメリットと将来性について考えていきましょう。
電力が自由化された日本

日本では「電気事業法」によって、特定の電力会社(現在10社)に対して、それぞれの地域で独占事業を認めるかわりに電力の安定供給を義務づけるという施策をとってきました。
しかし2000年代に入って、個人消費者の意識が電気も自由に好きな事業者から購入したいというマインドへと変化してきました。
そこで国は、段階的に電力自由化の流れを進めてきたのです。
まず発電の自由化を最初に認め、次に超高圧電力や高圧電力を販売する自由を認めました。
そして2016年4月から「小口電力販売自由化」が施行され、一般の消費者も電気を自由に購入できるようになったのです。
一般消費者向けの電力販売は7兆円以上の市場規模があり、そのうち3割が電気使用量が多い首都圏に集中しています。
首都圏に電気を供給している電力事業者は東京電力(東電)で、これまで独占状態となっていました。
それが電力自由化によって、さまざまな事業者がシェアを奪い合う状況となっています。
それでは電力自由化によって一般家庭の消費者にはどのようなメリットが生まれたのか、解説していきます。
電力自由化によるメリット
電力自由化によって一般の消費者にもたらされるもっとも大きなメリットは、電力を購入する事業者の選択肢が増えるということです。
これにより電力事業への参入を検討している企業は、一般の消費者を相手にしたビジネスチャンスが生まれました。
一方、消費者サイドも、これまで特定の電力会社からしか電気を購入できなかったところを、別の電力会社と契約して電気を購入できたり、新電力と呼ばれる参入事業者(ガス会社など)から買うこともできたりと、選択の幅が増えました。
これによって、契約者は電気料金を比較して、より安く電力を供給する電力会社に乗り替えたり、付帯サービスを受けたりすることができるようになったのです。
さらに、エネルギー関連企業ではない事業者が電気事業に参入した場合、メインの事業とセットで割引を行うなどのサービスも多様化します。
たとえば携帯電話の事業者が電気販売事業に参入した場合、携帯電話の通話料とセットでパッケージしたプランの提案なども可能となります。
これまで電気は特定の事業者からしか購入できず、価格も決められていた時代を考えれば、選択肢が広がったのは大きなメリットといえるでしょう。
ただし新電力事業者は顧客の囲い込みに注力していて、電気料金プランに契約期間を設け、期間内に契約を解除すると違約金が発生するといった料金メニューを用意している事業者もあるので、消費者はしっかりと業者を比べる必要があります。
アメリカの電力自由化

それでは、海の向こうの経済大国・アメリカの電力自由化はどうでしょうか。
日本に先んずること20年、1990年代からアメリカは「エネルギー政策基本法」によって電力自由化を施行しています。
送電線を所有しない発電事業者でも電力事業に参入できるようになり、送電線の開放も義務づけられました。
一般の消費者はどの電力事業者からでも電気の購入が可能となり、電力市場は顧客獲得競争がはじまったのです。
ただし、この施策は州ごとに電力自由化の推進が委ねられていて、進んでいる州と遅れている州が存在します。
電力自由化がスタートした時点では、20を超える州で法律が制定されるなど本格的な電力自由化が進むかに見えましたが、実際にはそう上手く進んでいないのが現状のようです。
アメリカの電力自由化の問題点

前述のように、アメリカでは電力自由化の推進が州ごとに委ねられたので、電力自由化が上手くいっている州、失敗した州、はじめから電力自由化を行わなかった州が混在している状況です。
そして電力自由化が施行された州でも、企業間の顧客獲得競争は依然として続いており、安定した市場にはなっていません。
ここでは、実際にアメリカで起こった電力自由化による問題について、具体例を挙げて紹介しましょう。
電力不足
アメリカの国を挙げて電力自由化を推進する波に、いち早く手を挙げたのがカリフォルニア州でした。
同州での電力自由化はスタート時に大きく歓迎され、多くの企業が電力事業へ参入しました。
しかし2000年夏、のちに「カリフォルニア電力危機」と呼ばれる電力供給不足により、停電が頻発する出来事が起こりました。
その原因は猛暑が発端ではあるものの、カリフォルニア州では発電所への環境負荷に対する規制が厳しいため、新たに発電所を建設するには、高コストの施設を設置しなければならず、結果として発電量が需要を下回ってしまったことでした。
この「カリフォルニア電力危機」では、電力価格が跳ね上がり、輪番停電(りんばんていでん)などが行われて大きな社会問題になりました。
輪番停電とは、電力の使用量が電力供給能力を上回ることで起こる「大規模停電」を避けるため、電力会社により地域ごとに電力供給を順次停止・再開させて調整することをいいます。
日本でも東日本大震災直後に行われたのは、記憶に新しいところです。
値上がり
電力自由化の大きなメリットとして、販売価格の自由化による競争が起こり、結果として電力価格が安くなるということが見込まれていました。
ところがアメリカでは、電力自由化が成功した州でも電力価格が下がるどころか、自由化を行っていない州よりも高くなっているという現象が起こっています。
これはどういうことなのでしょうか。
アメリカで、電力自由化を成功させている州として代表的なのが「テキサス州」です。
電力自由化が施行されて、一般消費者や企業のほぼ100%が従来の電力事業者から新規参入事業者へ乗り替えたというのです。
ただ、これは従来の一般電気事業者が顧客を失ってしまったわけではありません。
同州では電気の小売業者間で自由に競争が行われるよう環境を整備した一方で、従来の電気事業者には一般消費者と直接やり取りを行えなくしたために、すべての顧客を失ったかに見えるのです。
いわゆる、仲介業者を挟んだ電力の取引が行われるようになったのです。
発電施設を持つ従来の電気事業者は、新規参入事業者に送配電を行い、託送料金を請求しているといったからくりがあります。
これによって一般消費者は、元売りから仲介業者を通じて電気を購入するシステムに移行されてしまい、当然ながら中抜きが行われて電気代が上がってしまいました。
もちろん新規参入業者が電力を創出して、自由に価格設定をして販売することも可能です。
しかし、それを行うには新たに発電所を建設しなければならず、そのコストを考えれば電気料金に上乗せせざるを得ず、電気料金が安くなることはあり得えません。
結果として、電力自由化の本来の意図とは異なる方向で成功しているのが、テキサス州の電力自由化の実態といえます。
その他の先進国の電力自由化

電力自由化を実施している国はアメリカだけではありません。
イギリスやドイツなどの先進国も、すでに電力自由化を実施しています。
これらの先進国が電力自由化を実施して、一般消費者の生活はどのように変わったのか見ていきましょう。
イギリス
イギリスでは従来、国が経営する中央電力公社が電気事業を独占していました。
この中央電力公社は1997年に民営化され、国も経済不況を脱するために電力自由化に着手します。
そして1999年には、一般消費者向けの電力自由化が施行されることになります。
電力自由化が施行された当初は、電気事業者が発電した電力は強制的にプール市場へ集められる「強制プール制」が採用されました。
これは電気事業者が発電した電力を、国が強制的にプール市場に集めて一般消費者へ販売するという仕組みでした。
この強制プール制は、大手の企業が市場を容易に操作できるため、結局は価格が下がらないどころか、高騰してしまうという結果になりました。
結局、この強制プール制は2002年に廃止されNETAという制度を導入、さらに2005年にはBETTAという制度へと移行しました。
このBETTA導入後、電力市場は競争が発生し、効率的な取引が行われるようになりました。
現在では、電気事業者も一新され、国内外6社によるシェアという状況となっています。
ドイツ
ドイツもまた1998年に電力自由化の波が起こりました。
その際、現在の日本同様に100社以上の新電力事業者が参入してきましたが、既存の大手電力会社が対抗措置をとった結果、多くの新電力事業者が倒産してしまいました。
大手電力会社が設備投資を控え、電気料金を値下げし、反対に送電線の使用料金を高く設定したのです。
その結果、新電力事業者は価格競争に敗れ、ほとんどが廃業に追い込まれてしまいました。
ドイツにはシュタットベルケという、古くからの地元出資による公共事業の電力会社が1000団体ほどあり、高いシェアを持っていました。
このシュタットベルケが価格競争に勝ってシェアを維持し、新電力事業者が倒産した後に電気料金をじわじわと上げ、現在の状況となっています。
結局、電力自由化が施行されても、一般消費者は電力会社を乗り替えることができず、競争が起こったのもツカの間で最終的には何も変わりませんでした。
それどころか、現在では電気料金が自由化の前の水準よりも高くなっています。
日本でも欧米諸国と同じことが起こる?

日本での電力自由化が施行された、現在の状況を解説しましょう。
電力不足は起こりにくい
現在のところ、電力の小売が自由化され、多くの新電力事業者が参入しています。
日本ではドイツのように電力に関して公共事業の団体がありませんので、新電力事業者の参入は比較的容易で、予想通りシェア競争が起こっています。
ただしイギリスのように、公的な電力市場というものが整備されていませんので、結局は従来の電力会社が価格を操作することが可能のため、一般消費者は電気料金の値下げを実感できていません。
また日本では、アメリカの事例のように電力不足が起こって大規模停電が発生したり、輪番停電などが行われたりする可能性は極めて低いといわれてます。
なぜなら、新電力事業者が電力不足となっても、既存の10社ある電力会社がバックアップする仕組みとなっているからです。
たとえば関東であれば東電が、九州なら九州電力が電気を供給してくれます。
値上がりの可能性
現在でも、日本では送電システムを大手電力会社が押さえているため、アメリカのように新電力事業者に対して高い送電システムの使用料を要求しているため、電気料金の高騰が起こる可能性はゼロではありません。
また、価格設定に関しても電力自由化前は消費者庁によって値上げを行ってよいか、値上げの額はいくらといった規制料金制度が採用されていました。
これが電力自由化によって行われなくなったため、価格が自由に設定できるようになり、安くなる可能性もあれば高くなる可能性もあります。
実際、化石燃料や原子力に頼る日本の電力会社は、燃料費などの高騰によって少しずつ値上げをせざるを得ない状況にあります。
電力自由化を失敗しないために

日本の電力自由化を海外の事例を踏まえて考えてきましたが、いかがでしたか。
アメリカやイギリス、ドイツの例を見ても、電力自由化によって自由競争が起こり、一般消費者は安く電気を購入できるようになったという事例はひとつもありません。
こういった欧米の先進国による電力自由化の失敗例をもとに、我が国では適切な電力自由化を進めることがポイントになります。
近年、日本ではマンションなどを中心に電気メーターを「スマートメーター」と呼ばれるメーターに切り替えられているのをご存知でしょうか。
これは、大手電力会社が電力自由化が始まる前から無料で順次取替を行っているシステムで、電力の使用量をデジタルで計測する機械です。
従来の電力メーターでは、1ヶ月に1度検針をするアナログな計測方法でしたが、スマートメーターによって30分単位で電気の使用量を計測できるようになりました。
このスマートメーターによって太陽光発電など再生可能エネルギーと、電力会社から供給された電気とを区別することが可能となり、どの程度の電力をどの業者から購入するかという選択肢が増えました。
電力自由化を成功させるためには、コストパフォーマンスの高い電気供給の仕組み作りが不可欠です。
原子力などに頼らない、太陽光や水、風を使った発電にも注目が集まっています。
- 電力自由化によって消費者は自由に電気の購入先を選べるようになった
- アメリカでは電力自由化によって「カリフォルニア電力危機」と呼ばれる問題が発生した
- アメリカでは大手電力会社に送電設備を借りるため、電気料金を値上げせざるを得なくなった
- イギリスでは強制プール制によって電力自由化しても電気料金は値上がりした
- ドイツでは新電力事業者が競争に負けて電力自由化が形骸化した